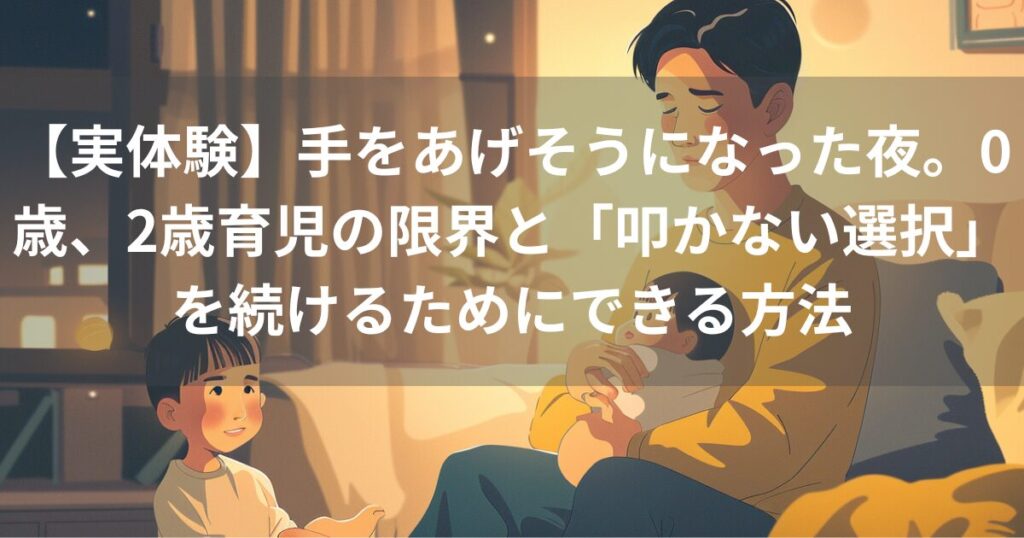
はじめに:イライラしない親なんていない
夜、ようやく0歳の赤ちゃんが泣き止んで、すやすやと寝始めた。
あぁ、ようやく少し静かになる…そう思った矢先、上の2歳がやってくる。
「ママ〜!ねぇねぇ!」
その声のあと、赤ちゃんのほっぺに足を乗せてみたり、
お気に入りのぬいぐるみをわざと投げてみたり。
「やめてって言ったでしょ!」
声を荒げたくなる。
せっかく寝かしつけた赤ちゃんが、また大泣き。
もう、こっちも泣きたい。
…この瞬間、手をあげそうになる。
頭では「叩いちゃダメ」とわかっているのに、体が反応してしまいそうになる。
そんな夜、ありますよね。
でもそれを「親失格」なんて思わないでほしい。
実は、その葛藤こそが“叩かない育児”のスタートラインなんです。
「叩くこと」はダメ。でも「叩きたくなる気持ち」は誰にでもある
「体罰禁止」という言葉、最近よく耳にしますよね。
実は2019年に児童虐待防止法と児童福祉法が改正され、
親が“しつけのため”であっても、体罰は禁止されました。
「軽くでもビンタ」「つねる」「押さえつける」「物を投げる」──
すべてが法律上“体罰”として扱われます。
ただ、ここで大事なのは、
「叩きたくなる気持ち」は自然な感情だということ。
イライラは、あなたが悪いからではありません。
脳科学的にも、育児中はホルモンバランスが乱れやすく、
「怒りのブレーキ」が効きにくくなることが分かっています。
寝不足、孤独、泣き声、家事のプレッシャー…。
普通の状態ではない中で、冷静さを保つほうが難しい。
だから、手をあげそうになる瞬間があるのは、
**“頑張ってる証拠”**なんです。
「なんで同じことを何回もするの?」の正体
上の子は、授乳中に体当たりしてきたり、
スマホを顔に投げてきたりすることもあります。
「何回言ってもわからない!」
「わざとやってるの?」
そう思ってしまうのも当然です。
でも実は、2歳くらいの子どもは「言葉より行動」でしか伝えられません。
「ママこっち見て!」という気持ちが、
叩く・投げる・邪魔するという行動で出てしまうんです。
つまり、あれは**“甘えのサイン”**。
赤ちゃんばかり見られていると感じるから、
「ぼくも見て!」「私のことも大事にして!」と体で訴えているんですね。
そう考えると、ちょっと見方が変わります。
叩くのをやめさせるより、
「どう甘えさせるか」を考えた方が、ぐっとラクになります。
🥢味噌汁に沈んだメガネ事件
ある日の夕飯中のこと。
上の子がスプーンで遊びながら、にこにこと笑っていました。
その勢いで──
私のメガネをパシッとはたいて落としたんです。
よりによって、落ちた先は味噌汁の中。
メガネは味噌の海に沈み、湯気がほんのり立ち上がっていました。
一瞬、頭が真っ白。
「あー、もう!」って声が出かけた。
でも、その時ふと思ったんです。
「叩いたらダメ、こういう時こそ冷静に」
だから、深呼吸してこう言いました。
「メガネ叩いたらだめだよ」
それだけ言って、黙ってメガネを洗い、またかけました。
子どもはびっくりした顔でこちらを見て、
そのあとは静かにごはんを食べてくれました。
その夜、私は少しだけ誇らしい気持ちになりました。
怒鳴らなくても、ちゃんと伝わることがあるんだと。
「叩かない」を続けるためにできる3つの工夫
① 「待ってて」じゃなく「あとで一緒にやろうね」
授乳中や赤ちゃん対応中に上の子が邪魔してきたら、
「今はダメ」よりも「あとで一緒にやろうね」と伝えてみてください。
“待ってて”だけでは、2歳児には伝わりません。
“後で”があると、気持ちが落ち着きます。
② 1日5分だけでも“上の子だけの時間”をつくる
たった5分でも抱っこして話す時間をつくるだけで、
「ママはちゃんと自分を見てくれてる」と安心します。
寝る前のハグでも、歯磨きのあとでもOK。
③ 叱るより“環境で防ぐ”
危険なもの、投げやすいおもちゃ、
触ってほしくない物はあらかじめ手の届かない場所へ。
行動そのものを起こせないようにすることで、
「叱る回数」を減らせます。
💭 叩かないって、我慢じゃなく“準備”
子どもが泣き止まない、夜泣きが続く、
上の子がちょっかいを出して赤ちゃんがまた泣く。
そんな毎日の中で、私が少しずつ学んだのは、
**「叩かないためには、想定しておくことが大事」**ということ。
「また泣くかも」
「また上の子が邪魔してくるかも」
そういう“もしも”を頭の中で準備しておくだけで、
実際に起きた時のイライラが少し和らぎます。
そして、もし本当にイライラが限界になったら、
その場から離れる勇気を持ってください。
トイレにこもるでもいい。
窓を開けて深呼吸するでもいい。
「手をあげる前に離れる」──それだけで十分。
🌸未来の自分に言ってあげたいこと
正直、毎日ドタバタで、
「私、ちゃんと育児できてるのかな…?」って思う日もあります。
でも、味噌汁に沈んだメガネを洗って、
それでも優しく声をかけたあの日を思い出すと、
「あ、ちゃんと成長してるな」って思えるんです。
叩かない育児は、完璧を目指すことじゃない。
失敗しても、泣いても、怒っても、
「次は叩かずに済むように考える」
その積み重ねが、子どもの安心を育てていくんだと思います。
いつかこの子たちが大きくなったとき、
「ママ(パパ)怒ってたけど、叩かれたことなかったね」
って笑って話せたら、それでいい。
✅まとめ:叩かない育児の5つの心得
- 2020年4月1日年以降、体罰は法律で禁止
どんなに軽くても、体に負荷を加える行為はNG。 - 「叩きたくなる気持ち」は自然な反応
親を責めない。感情を持つのは普通のこと。 - 子どもの問題行動は「甘えのサイン」
言葉で伝えられないから、行動で見せている。 - 叱るより「防ぐ」方が効果的
環境づくりと心の準備で、手が出る前に対応。 - 完璧を目指さない。離れて深呼吸でもOK
叩かないために“自分を守る”のも立派な育児。
🌙おわりに
泣いて、怒って、笑って、また泣いて。
育児って、本当にドタバタです。
でも、そんな日々の中であなたが「叩かない」を選んでいる限り、
それは子どもにとって最高の安心です。
今日もまた、メガネを洗って立ち上がるあなたへ。
その一歩一歩が、ちゃんと愛になってます。
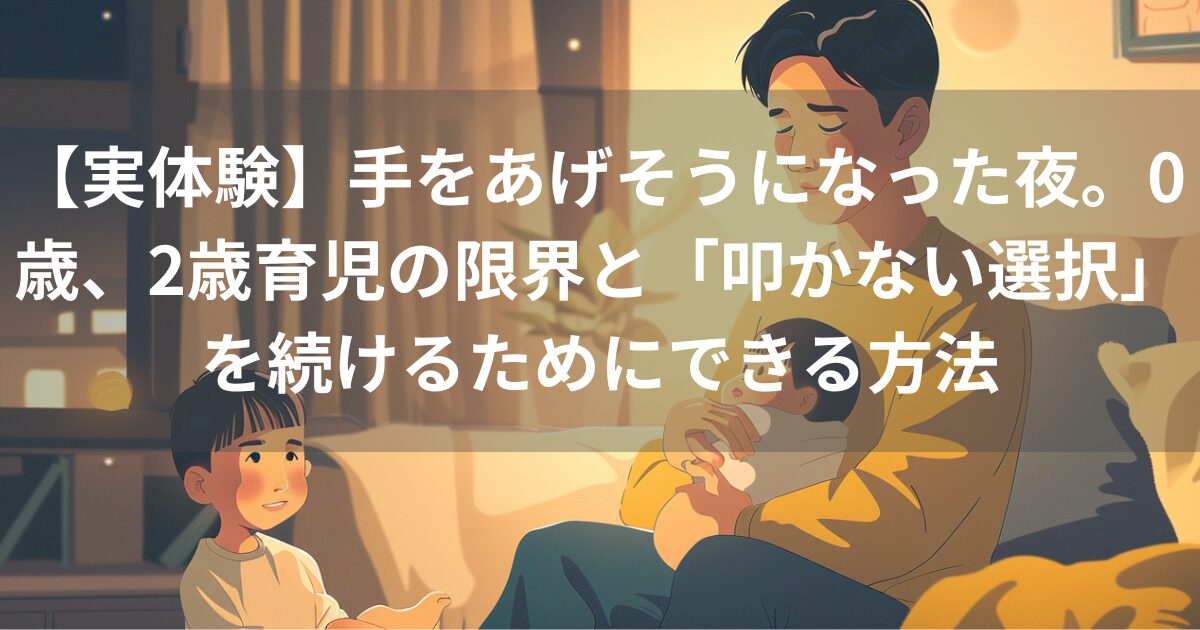


コメント